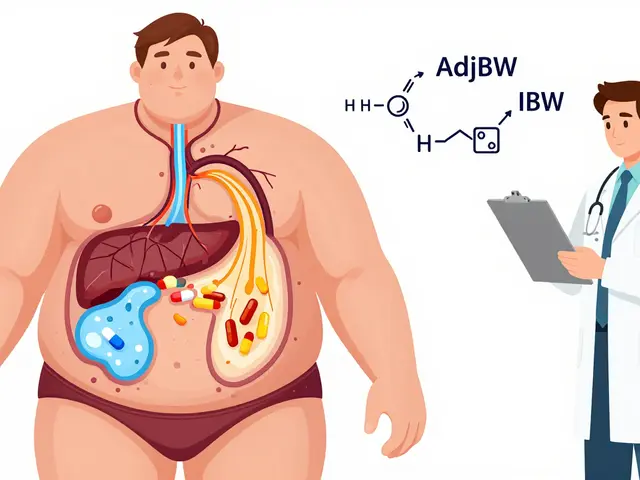多発性硬化症(MS)の予後を知りたいあなたへ
多発性硬化症は、神経が自分の免疫で攻撃される病気です。診断を受けたとき、まず気になるのが「この後、どうなるの?」という予後です。予後は人それぞれですが、いくつかのポイントで大まかに予測できます。
症状の進行パターンと予後の目安
MSは大きく「再発寛解型(RRMS)」「進行型(SPMS・PPMS)」に分かれます。RRMSは発作と回復が交互に起き、治療で症状を抑えやすいです。10〜15年で徐々に進行型に移行するケースが多いですが、早期に病状をコントロールすれば、日常生活への影響を最小限に抑えられます。
一方、一次進行型(PPMS)は診断時から症状がゆっくり悪化し、再発と回復のサイクルがありません。予後はやや厳しい傾向にありますが、近年は新しい薬が効果を示しているので、治療の選択肢は増えています。
予後に影響する重要な要素
1️⃣ 発症年齢:30代前半で発症すると、長い治療期間が必要になる分、予後がやや不利です。逆に50代以降の発症は進行が遅いケースが多いです。
2️⃣ 発作の頻度と重症度:短期間に何回も重い発作があると、神経損傷が蓄積しやすく、将来的な障害が残りやすいです。
3️⃣ 治療開始のタイミング:診断後すぐに免疫調整薬を始めると、再発リスクが下がり、長期的に見て予後が良くなることが研究で示されています。
4️⃣ リハビリと生活習慣:定期的なリハビリや適度な運動、バランスの良い食事は筋力低下や疲労感を抑え、生活の質(QOL)を保つのに役立ちます。
実際のケースを見てみましょう。Aさん(34歳・RRMS)は診断後すぐに免疫調整薬とリハビリを開始。10年後も仕事は続けられ、日常生活での支障は軽いです。逆にBさん(42歳・PPMS)は診断が遅れ、薬の導入も遅かったため、歩行障害が進行し、車椅子使用が必要になりました。
このように、早期治療と継続的なケアが予後を左右します。医師と相談しながら、自分に合った薬とリハビリプランを作ることが大切です。
最後に、予後を「絶対的」ではなく「可能性」と捉えてください。最新の治療法は日々進化していて、昔は考えられなかった生活の質向上も実現可能です。疑問や不安があるときは、遠慮せず専門医に質問しましょう。あなたができることは、情報を集めて行動することです。

CIS(臨床的孤発症候群)における神経心理学的検査の役割:早期発見と予後予測の実践ガイド
CISでの認知変化は早期から起こりやすい。神経心理学的検査の使い方、推奨テスト、解釈、実装のコツ、予後予測や治療判断への活かし方を実務目線で解説。
続きを読む