初発の視神経炎や脳幹症状でCIS(臨床的孤発症候群)と告げられたとき、多くの人が気にするのは「多発性硬化症(MS)に進むのか」と「仕事や日常に支障が出るのか」です。見逃されがちなのが、運動や感覚よりも先に静かに進む“認知の変化”。ここを素早く、客観的に、繰り返し測れるのが神経心理学的検査です。この記事では、CISで何をいつ測るか、どのテストを選ぶか、結果をどう治療と生活支援に結びつけるかを、現場ですぐ使える形でまとめます。過度な期待は禁物ですが、正しい手順を踏めば、予後予測と早期介入の質が一段上がります。
TL;DR/要点サマリー
クリックして知りたかったことに、まず短く答えます。
- CISでも約20〜35%で処理速度などの認知低下が見つかる。見逃すと復職・学業・QOLの落ち込みが大きい。
- 最小構成はSDMT+記憶(CVLT-II/BVMT-R)+注意/実行機能(TMTやStroop)。所要20〜30分のBICAMSが汎用。
- ベースライン(診断時)→6〜12カ月→年1回が基本。治療変更時や再発時も再評価。
- 有意な低下の目安はSDMTで4点または10%低下。抑うつ・疲労・睡眠の影響は必ずスクリーニング。
- 認知低下はMS移行リスクやMRIの深部灰白質萎縮、血清NfL上昇と関連(複数研究)。早期DMT導入やリハで改善余地あり。
実装ステップ:CIS診療に“認知”を組み込む方法
目的は3つ。1) 初期ダメージの可視化、2) 進行の早期検知、3) 生活と治療の意思決定支援。やることはシンプルです。
- はじめに決めること(外来フロー設計)
- 検査タイミング:診断時(または発症後3カ月以内)をベースライン。次は6〜12カ月、その後は年1回。
- 担当:心理士/作業療法士/検査トレーニング済みスタッフ。結果の説明は神経内科医と共有。
- 同時に取る共変量:抑うつ(PHQ-9/HADS)、不安(GAD-7)、疲労(MFIS/FSS)、睡眠(PSQI)、教育年数/職業。
- バッテリーを選ぶ(20〜30分で回せる現実路線)
- 処理速度:SDMT(口頭版/筆記版)
- 言語記憶:CVLT-II(短縮版でも可)
- 視覚記憶:BVMT-R
- 代替・補助:TMT-A/B、Stroop、PASAT(疲労を強めるので慎重に)
- 短時間ならBICAMS(SDMT+CVLT-II+BVMT-R)が定番。日本語版の利用可否を確認。
- 測定条件を整える(誤判定を防ぐ)
- 発熱・再発直後・極端な睡眠不足を避ける。服薬(鎮静性)も記録。
- 検査は午前帯、45〜60分で完了。休憩を挟み、順序は固定。
- 再検時は同条件を再現。学習効果を見込んだ解釈(等価版がある場合は交互使用)。
- 判定のルール(Zスコアと臨床的意味)
- 各テストを年齢・教育年数で標準化(Zスコア)。-1.0未満を軽度低下、-1.5未満を明確な低下の目安。
- 縦断での有意低下:SDMTは4点または10%のドロップを警戒ラインとして扱うのが実務的。
- 領域横断の判定:2領域以上でZ≤-1.0なら介入検討。1領域でも機能障害を伴えば同様。
- 治療と支援につなぐ
- 疾患修飾療法(DMT):MRI活動性や寡多髄液オリゴクローナルバンド、血清NfLと併せて総合判断。認知低下が悪化傾向なら早期強力療法を検討。
- ノンファーマ:認知リハ(処理速度トレーニング)、就労支援(業務の負荷設計、在宅・柔軟勤務)、睡眠・運動・ビタミンD最適化。
- 説明:本人と家族に“見える化”して共有。目標設定(例:SDMT+3点、タイピング精度95%)を短期・中期で。
何を測る?推奨テスト、時間、カットオフ、読み解き方
CISで頻度が高いのは、処理速度の低下、エピソード記憶(言語・視覚)、注意・実行機能の軽度障害です。ここでは“使える道具”の中身を、現実の外来時間に合わせて整理します。
| ドメイン | 推奨テスト | 時間 | 有意低下の目安 | 現場のコツ |
|---|---|---|---|---|
| 処理速度 | SDMT | 5分 | Z≤-1.0(横断)/4点or10%低下(縦断) | 最も敏感。口頭版は視力の影響が少ない。 |
| 言語記憶 | CVLT-II(短縮可) | 10-15分 | Z≤-1.0 | 学習曲線を見る。抑うつの影響を考慮。 |
| 視覚記憶 | BVMT-R | 10分 | Z≤-1.0 | 視神経炎後は適切な照明と距離で。 |
| 注意・セット転換 | TMT-A/B | 5-7分 | Z≤-1.0/B-A差も評価 | 衝動性・視空間の影響もメモ。 |
| 抑制・選択的注意 | Stroop | 5分 | Z≤-1.0 | 色覚の確認。疲労でばらつきやすい。 |
解釈の柱は「一貫性」と「臨床的関連性」です。単発のZ≤-1.0は“サイン”。複数領域の低下や、本人が困っている機能(仕事の速度、マルチタスク、記憶ミス)と一致するなら“シグナル”。また、縦断での小さな悪化でも、MRIで新規T2病変や脳萎縮の進行、血清NfLの上昇が並ぶときは、治療の見直しを真剣に検討します。
参考となるエビデンス:
- 認知障害の有病率:CISで約20-35%(Amatoら 2010; Ruetら 2013; Plancheら 2016)。
- 処理速度(SDMT)はCIS/早期MSで最も安定した指標(Benedictら 2017 BICAMS国際コンセンサス)。
- 認知低下は深部灰白質(視床)容積低下や拡散異常と相関(Rocca/MAGNIMS 2015-2021)。
- 血清NfLは疾患活動性と関連し、認知とも連動する報告(Kuhleら 2019; Barroら 2020)。
- MS診断基準の枠組み:2017 McDonald基準(Thompsonら 2018)。CIS段階でもリスク層別化が鍵。

ケースで学ぶ:判断・治療・生活支援のつなぎ方
具体例のほうが腹落ちします。実際に近い3つのシナリオで考えます。
- ケース1:視神経炎のCIS、業務の遅れが目立つ20代
ベースライン:SDMT Z=-1.2、CVLT-II Z=-0.5、BVMT-R Z=-0.7。MRIは視神経炎所見+脳内T2病変2個、CSF OCB陽性。6カ月:SDMTが-4点(10%低下)、新規T2病変1個。仕事でメール返信と文書作成が遅い。
対応:DMTの早期強化を選択。就労面は「朝のコア業務」「通知オフ」「会議は30分」を試行。認知リハは週2の処理速度トレーニング。3カ月でSDMT+3点、自己効力感が戻る。 - ケース2:感覚障害のCIS、学業中の30代院生
ベースライン:SDMT Z=-0.8、CVLT-II Z=-1.3、BVMT-R Z=-1.1。抑うつ軽度(PHQ-9=7)。MRIは病変散在。
対応:言語・視覚記憶の弱さに焦点。講義録音と“想起練習”をセット、学習はポモドーロ法25分。抑うつには軽運動と睡眠介入。6カ月でCVLT-II Z=-0.8へ改善、研究の期限遵守率が上がる。DMTは活動性低いが、本人の希望で導入。 - ケース3:症状は軽快、でも疲れやすい40代会社員
ベースライン:SDMT Z=-0.6、他は正常。疲労(MFIS高値)。MRIは静穏。
対応:病的認知低下はなし。疲労マネジメント(ペーシング、クーリング、昼寝15分上限)を優先。テストは年1回のフォロー。仕事は「午後の高負荷作業を避ける」だけでパフォーマンスが安定。
ポイントは、検査結果を“数値で語る”だけで終わらせないこと。本人の目標(仕事、育児、研究、資格試験)に直結する小さな介入を即日提案し、次回までの実験計画に落とす。これが継続の原動力になります。
チェックリスト&実務チートシート
忙しい外来でそのまま使える形に圧縮しました。印刷してカルテ裏に貼ってもOK。
- 誰をいつ測る?(意思決定ツリー)
- CIS診断時は全員ベースラインを取る
- 次のどれかがあれば6-12カ月で再検:MRI新規病変/血清NfL上昇/復職・復学の予定/自覚的な遅さ・物忘れ
- 年1回の定期検査を基本。治療変更・再発・重い疲労時も追加。
- 最低限キット(20-30分)
- SDMT、CVLT-II、BVMT-R(=BICAMS)
- 補助:TMT-A/B、Stroop
- 併用スクリーニング:PHQ-9、MFIS、PSQI
- 警戒ライン(アラート)
- SDMT 4点または10%低下(縦断)
- 2領域以上でZ≤-1.0(横断)
- 本人の新たな機能障害(締切遅延、ケアレスミス増加)
- よくある落とし穴
- 視力低下や色覚異常を補正せずに視覚テストを実施
- 抑うつ・疲労を“性格”で片付けて共変量に入れない
- 学習効果を無視して短期間に同一版で再検
- 数字だけで説明して、生活の具体策に落とさない
- プロの小ワザ
- SDMTは最初の30秒と後半30秒の差も記録(持久力のヒント)。
- 本人が大事にする指標(タイピング速度、メール未処理数)を“第4のアウトカム”に。
- MRIは視床・尾状核など深部灰白質のボリュームもレポート依頼。
| 指標 | CISでの所見 | 予後との関係 | 代表的エビデンス |
|---|---|---|---|
| SDMT | 20-30%で低下 | 低値はMS移行・萎縮進行と関連 | Benedict 2017; Amato 2010; Ruet 2013 |
| 記憶(CVLT-II/BVMT-R) | 10-25%で低下 | 日常機能低下と関連 | Planche 2016; BICAMS国際データ |
| 血清NfL | 活動性で上昇 | 高値は認知悪化と併走 | Kuhle 2019; Barro 2020 |
| MRI深部灰白質 | 視床容積の早期低下 | 処理速度と相関 | Rocca/MAGNIMS 2015-2021 |
数字は施設や母集団でぶれます。大切なのは、同じ人の“軌跡”を同じ物差しで追うことです。
FAQ&次の一手/トラブルシューティング
よく出る疑問と、状況別の打ち手をまとめました。
- Q. CISで標準的に必須ですか?
A. ガイドラインで「絶対必須」とは言い切られていませんが、早期からの認知低下は珍しくなく、治療と就労・就学の意思決定に役立つので、ベースライン取得は強く推奨します。 - Q. どのくらいの変化なら“本物の悪化”?
A. SDMTなら4点(または10%)低下を目安に。できれば練習効果を補正した信頼性変化指標(RCI)で判定します。 - Q. 疲労や抑うつの影響をどう分ける?
A. 同日にPHQ-9、MFIS、PSQIを取り、カットオフ超えの場合はまずそちらを介入。再評価で持続する低下のみを“器質的”と見ます。 - Q. 視神経炎後で視覚テストが不利では?
A. その通り。視力補正、適切な照明・距離、口頭版SDMTの併用でバイアスを減らします。 - Q. BICAMSで十分? もっと詳しくやるべき?
A. 外来ではBICAMSで十分なことが多いです。仕事で実行機能が問題ならTMT-BやStroopを足します。研究や訴訟など厳密さが要るなら包括的バッテリーを。 - Q. 認知低下が見つかったらDMTをすぐ強化?
A. 単独では決めません。MRI・CSF・NfL・再発歴と合わせて総合判断。複数指標で進行の一致があるときは強化の議論を。 - Q. 在宅や遠隔でできますか?
A. SDMTは遠隔版のエビデンスが増えています。環境コントロール(静音、回線、カメラ位置)と同一条件の再現を徹底すれば、有用なトラッキングが可能です。
状況別の次の一手
- 患者さんに“伝わる”説明がしたい:グラフで自分のスコアの推移と同年代平均を示し、今日からできる2つの具体策(例:通知オフ時間/25分学習)を紙で渡す。
- 時間がない:BICAMSだけ先に実施。抑うつ・疲労は超短縮版(PHQ-2、FSS-9)。次回に詳細。
- 結果がバラつく:睡眠・服薬・時間帯・カフェインを記録してプロトコル化。同条件で再検。
- 院内に実施者がいない:看護師・リハ職に30-60分のトレーニング。等価版の管理と手順書を作る。
- 保険・コストが気になる:短時間テストを主軸にし、必要時のみ包括バッテリーへ段階的に。
最後に、CISの“いま”をもう一度。認知のサインは小さく、でも生活への影響は大きい。検査で見える化し、治療・リハ・働き方に素早くつなぐ。この地道なループが、MS移行の抑制とQOLの維持に寄与します。神経心理学的検査は、そのループの最初のスイッチです。

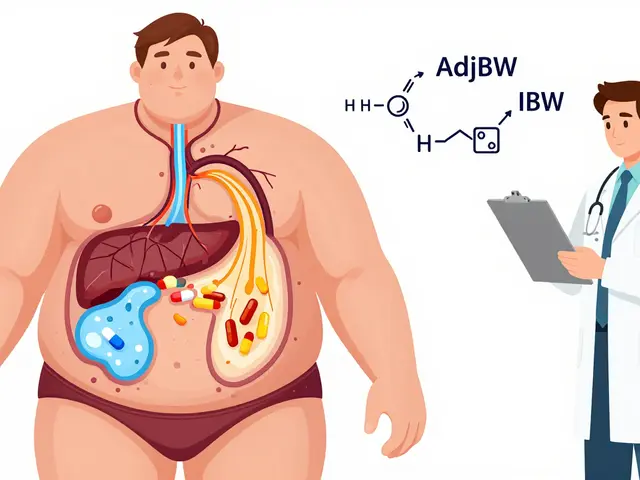





コメント
門間 優太
7 9月 2025この記事、本当に実践的で助かる。特にBICAMSの導入と、抑うつ・疲労のスクリーニングを併用する部分は、現場の負担を減らす仕組みになってるよね。今まで認知検査って“余裕があれば”って感じだったけど、これなら毎回やれる気がする。
JP Robarts School
9 9月 2025ここのデータ、全部製薬会社の意向で捏造されてるんじゃない?SDMTが“最も敏感”って書いてあるけど、あれは単に測定しやすいだけ。本当の認知機能は、会話の流れや記憶の連鎖でしか測れない。NfLも、ただの炎症マーカーで、脳の“意味の喪失”は測れない。この手の検査は、患者を薬漬けにするための方便だ。
Mariko Yoshimoto
9 9月 2025えーっと…この記事、本当に「BICAMS」って略語、日本語版で正式に使われてるんですか??? あと、CVLT-IIの「II」ってローマ数字なんですが、全角で書くべきじゃないですか??? それに、TMT-A/Bのスラッシュ、全角にしないと日本語の文法的に違和感あるんですけど…?????
HIROMI MIZUNO
10 9月 2025これ、めっちゃ役立つ!特に「本人の目標に落とす」って部分、救われた。私も仕事でタイピング遅くて悩んでたけど、SDMT+3点って目標設定してみたら、ちょっとずつ楽になった!
リハも週2回でいいって聞いたから、頑張れる!
みんなも、無理せず“小さな成功”を積み重ねてね!
晶 洪
11 9月 2025検査で数値を出すだけでは意味がない。本人が諦めたら、どんなテストも無意味だ。心が折れてる人間を、数字で評価するな。
naotaka ikeda
12 9月 2025ケース1の20代の患者さん、SDMTの4点低下でDMT強化したけど、その前に生活リズムの見直しは試したのか?睡眠不足とカフェイン過剰でテスト結果が悪化してること、よくある。検査前に「前日どれだけ寝たか」を記録する仕組み、必須だと思う。
諒 石橋
13 9月 2025日本はこんなに細かい検査を導入してるのに、アメリカは「患者が困ってるなら薬出せ」で済ませてる。日本人は過剰に神経質すぎる。この記事の内容、アメリカの病院でやったら「余計なことしすぎ」って怒られるぞ。我々の医療は、過剰診療の温床だ。
risa austin
14 9月 2025本稿は、臨床的孤発症候群における神経心理学的評価の体系的かつ実用的なアプローチを、明確かつ厳密に提示している。特に、縦断的評価における有意低下の定義、およびその臨床的意味づけに関して、極めて高次な知見を提供している。本稿の価値は、実践的ツールとしての完成度に存する。
Taisho Koganezawa
15 9月 2025でも、これって「検査できる人」がいないと意味ないよね?
日本では、心理士が足りないし、看護師にやらせるにはトレーニングが足りない。
だったら、AIで自動採点できるアプリ作ったら?
SDMTの音声を録音して、反応時間とミスをAIが分析。データはクラウドに保存。
これ、技術的にはもう可能なんじゃない?
なぜ、人間の手作業にこだわるの?
医療は、効率と公平性を追求すべきじゃないの?
Midori Kokoa
16 9月 2025この記事、本当に救いになった。認知の低下って、見えないから自分でも気づかない。でも、これで自分の状態がちょっとだけ見えるようになった。ありがとう。